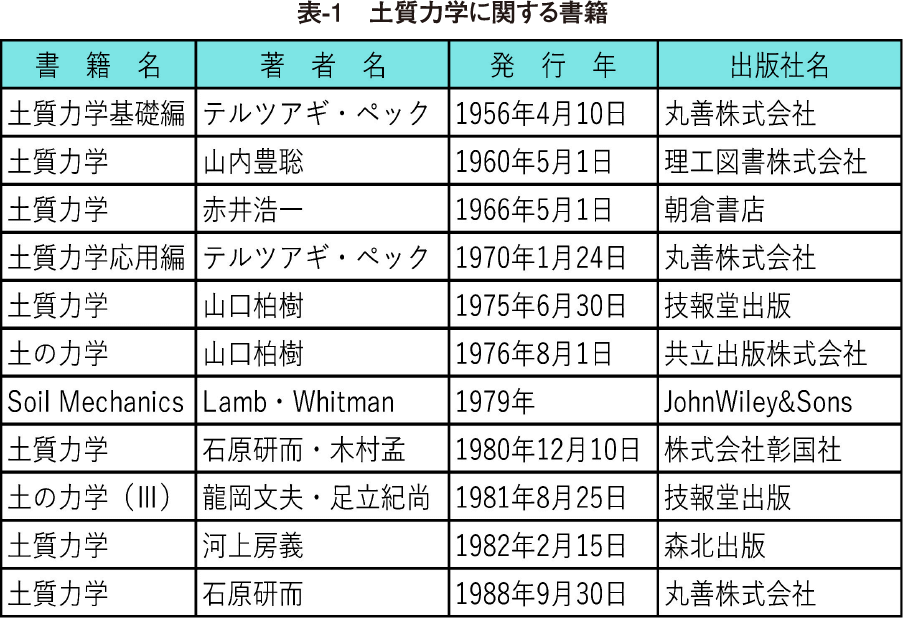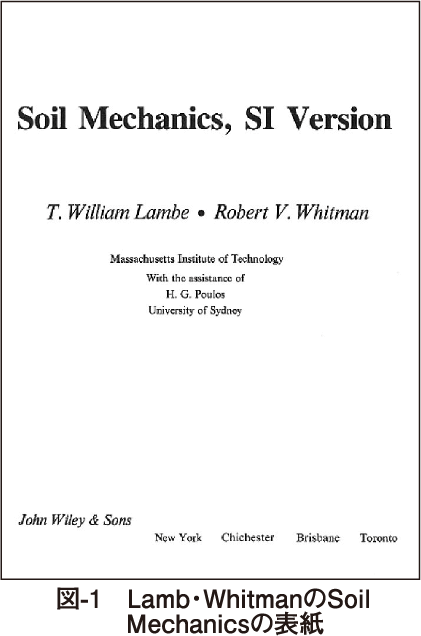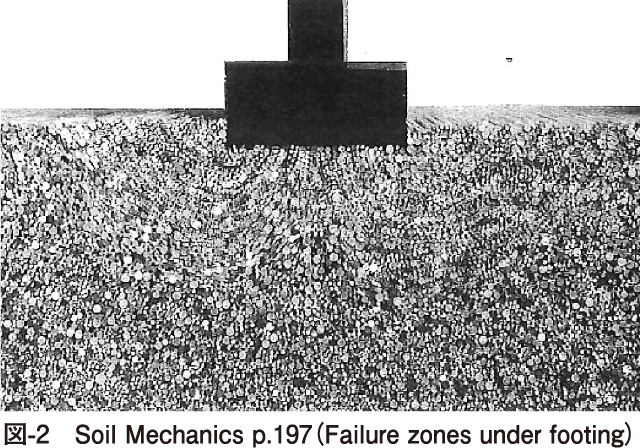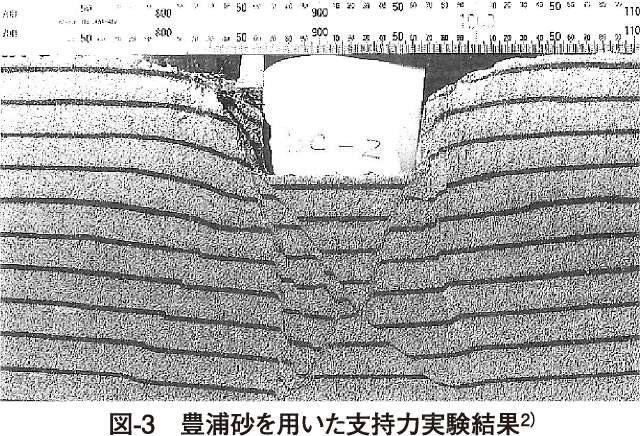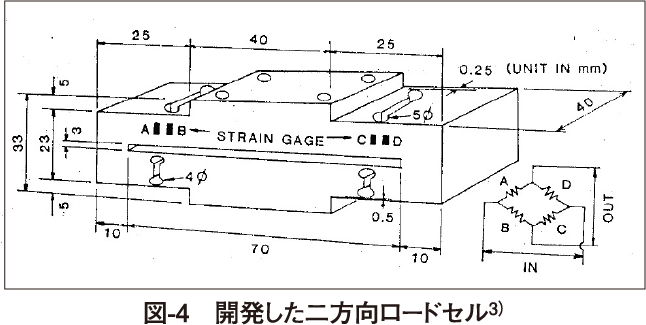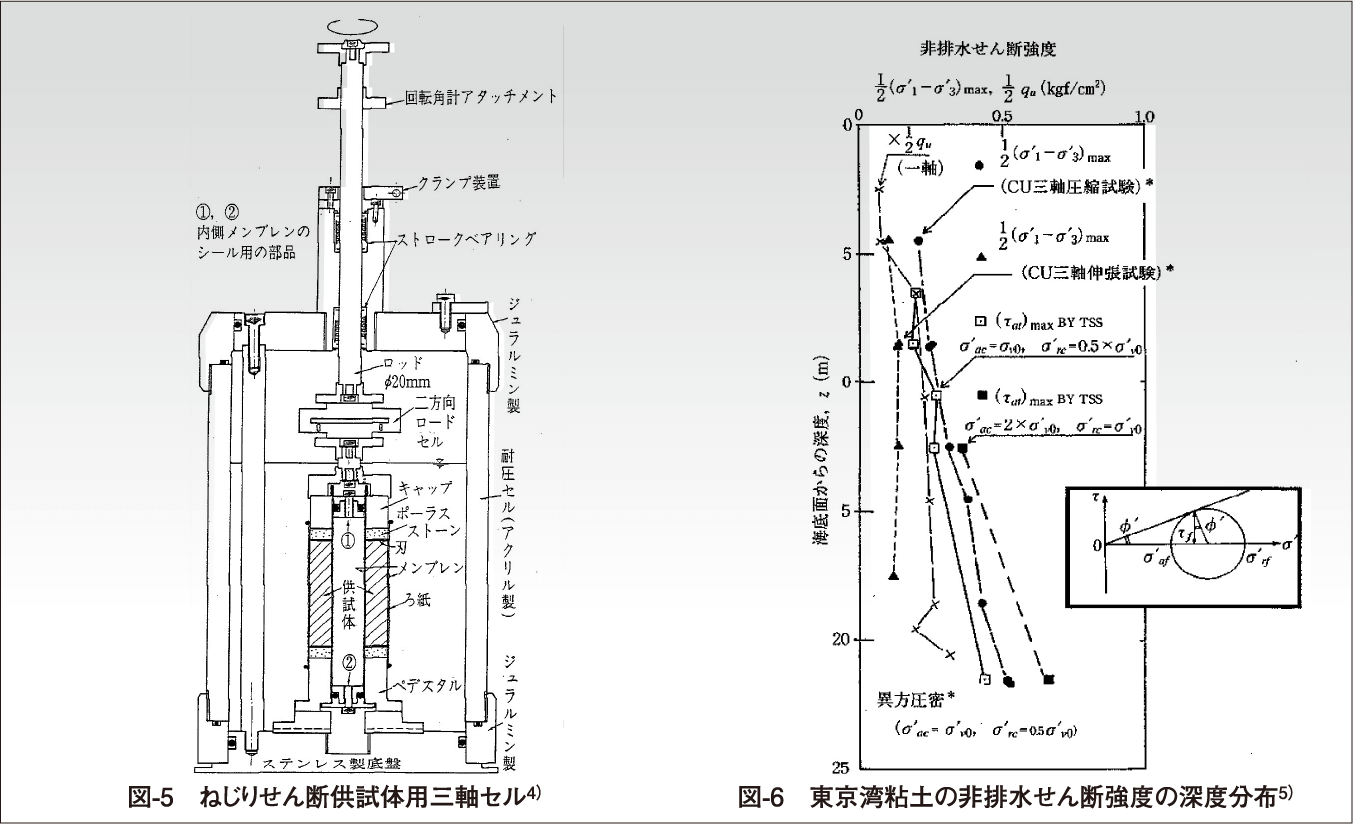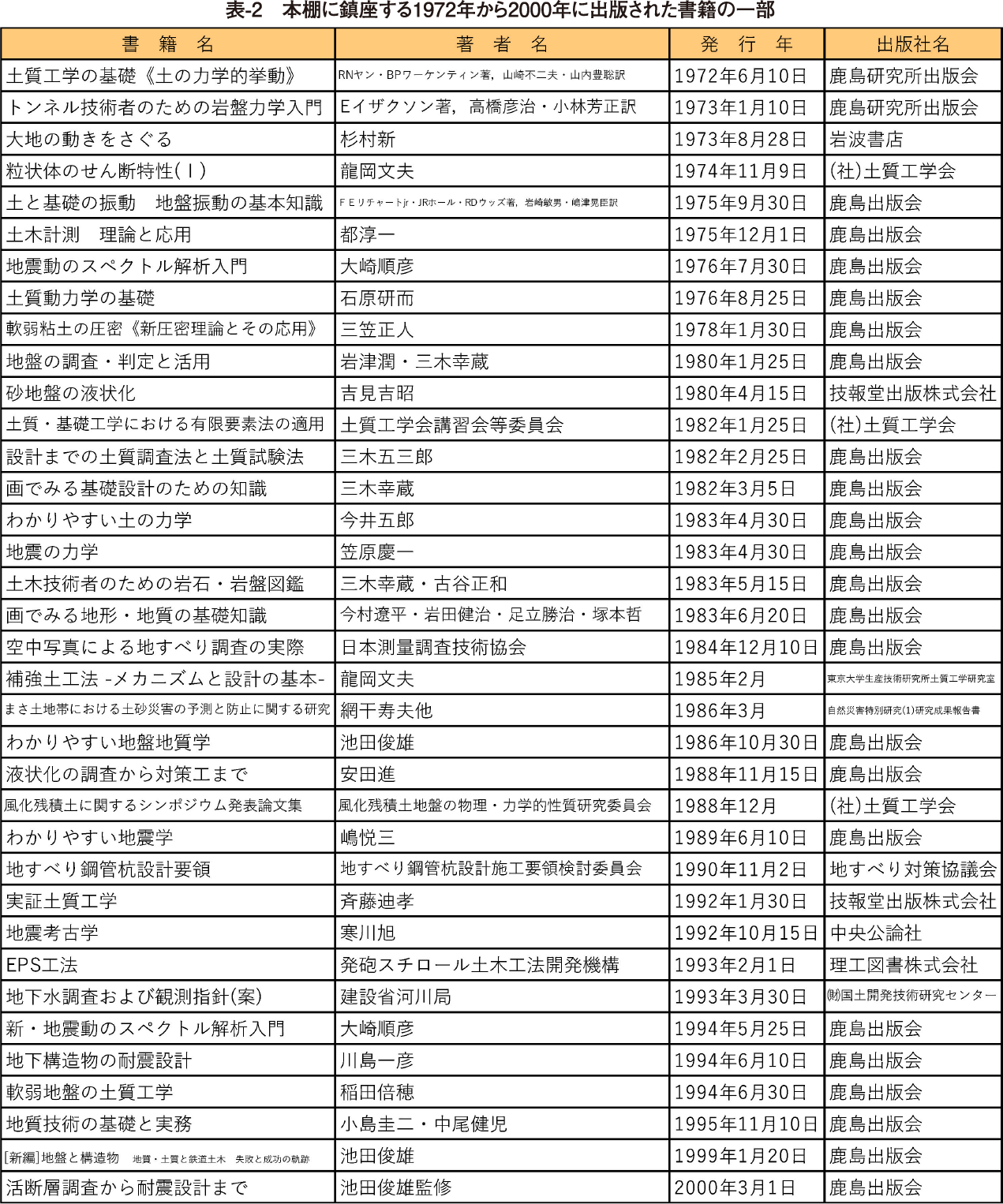土質力学の源流1)は、今から200年以上前のCoulomb(クーロン)の摩擦則によるせん断強度式とRankine(ランキン)の塑性平衡条件下における応力解析法までさかのぼります。これらは、土圧,斜面崩壊,基礎等の解析・設計において種々の工夫が施されて、現在も実務で活用されています。地下水流に関しては、Darcy(ダルシー)法則に基づく透水解析法が地盤中の水の浸透問題を解く際の基本的な方策となっています。また、道路,堤防,ため池,高フィルタイプダム等の盛土構造物の設計・施工に必須の基本情報となっているProctor(プロクター)が見出した「土粒子は破壊されないという仮定の下においては、密になると間隙比が小さくなり、最大の締固め密度を生むような含水状態が存在するという最適含水比の存在を示した締固めの原理」は、理論的な裏付けにはなっていないものの実務で用いられています。また、Terzagi(テルツアギー)は、土材料や地盤の応力~変形~強度特性を「有効応力の原理」により論じ、圧密モデルを作成しました。これも軟弱地盤解析の実務において圧密沈下の計算に用いられています。
つまり、地盤力学は、CoulombやRankineの古典的な土の力学にDarcy法則やProctor原理及びTerzagiの有効応力の原理等を取り込みながら、土が保有する粒子論的な意味での基本物性を吟味し、実務に適用するように発達してきたと言えます。
小生は、1974年に土木工学科に入学し、土質力学(その当時は土質工学Ⅰの講座)を専攻したのは、2年生になった時の講義において、森芳信教授が「土質は、鉄やコンクリートなどの土木(建設)材料に比べて難解だ」と言ったことがきっかけでした。(社)土質工学会(現:公益社団法人地盤工学会)に入会したのは4年生(1977年)の時になります。それ以来、43年間土質(地盤)に係わる実験・研究,調査・試験・計測及び設計などの業務を行ってきました。
お話を続ける前に土質や地盤に関係する言葉を整理しておきます。まず、土・土質(soil)と岩(rock)は、土と岩を区別する場合に用いることが多く、その当時は、土質力学(soil mechanics)と岩盤(石)力学(rock mechanics)と呼ばれていました。現在は、これらを併せて地盤力学(geo-mechanics)と称することが多くなっています。このため、土質工学(soil engineering),岩盤工学(rock engineering)も土質工学会が地盤工学会に変わったように地盤工学(geotechnical engineering)と称するようになっています。
したがって、ここでは、土質力学,岩盤(岩石)力学,土質工学,岩盤工学,地盤力学及び地盤工学という言葉を用いることにします。
![新協地水株式会社[土と水の総合コンサルタント]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2018/08/logo.png)
![思い出の地盤工学(1)[シリーズ3回]](http://www.sinkyo-tisui.co.jp/wp-content/uploads/2020/03/75-04-01.png)